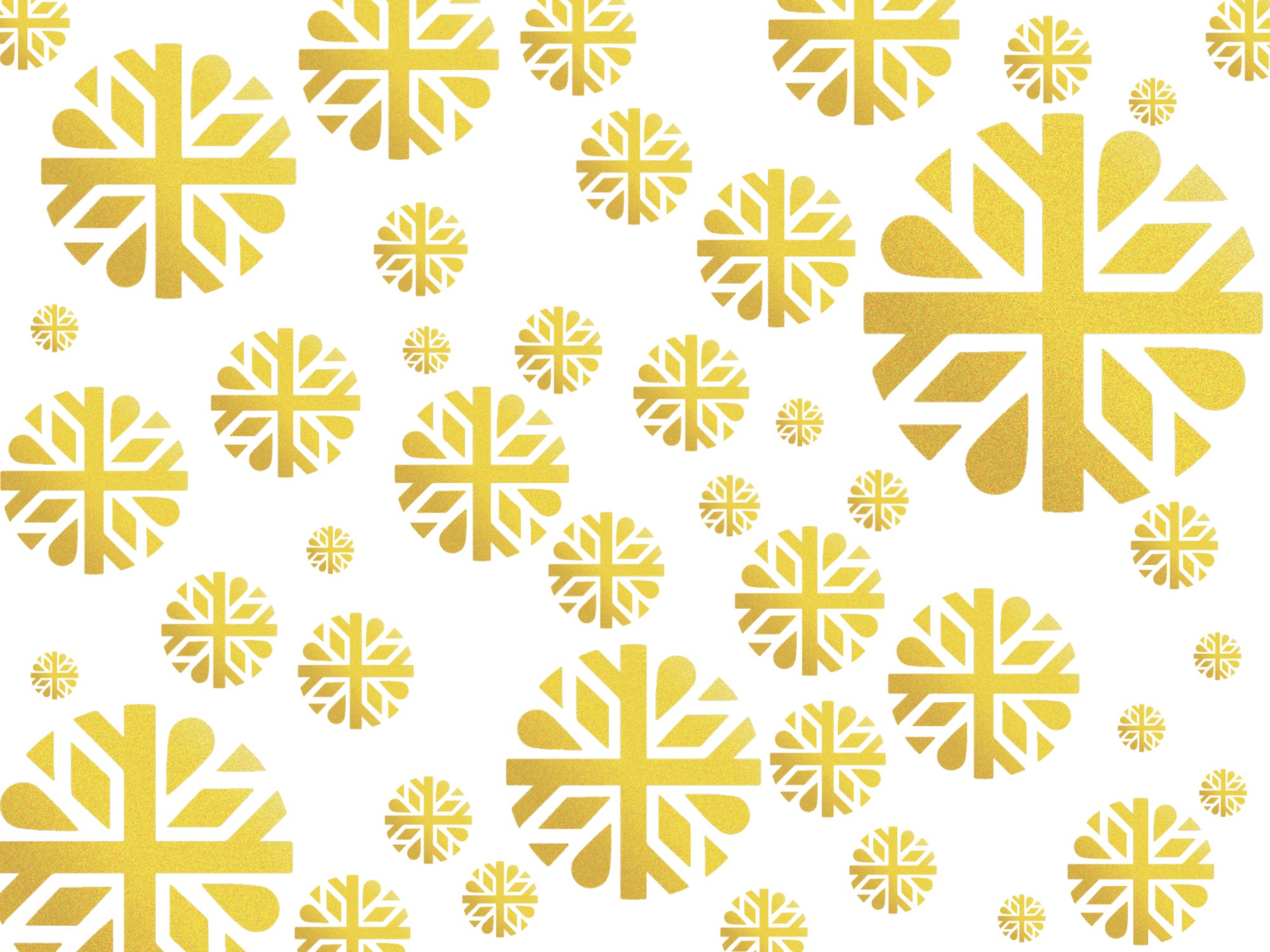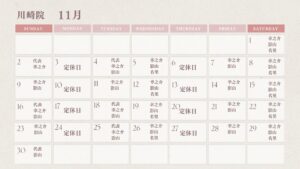「痛い=ケガをした時」だと思っていませんか?
こんにちは。Bianca鍼灸サロンです。
今回は『痛み』について記事を書きました。
実は痛いという感覚は、「脳が痛みとして処理する」ことで感じるものなのです。
- 痛みとは
- 痛みの役割
- 痛みが及ぼす悪影響
- 東洋医学から見た痛み
Biancaブログでは患者様が気になっていることをブログにしております。
他にもこんなことも知りたいなどあれば、お問い合わせください。
皆様、最後までお付き合いいただければ幸いです。
痛みとは
痛みとは、単に身体の不快な感覚だけではなく、「身体的・精神的に重要な意味を持つ防御反応」です。
「痛み」と「疼痛」はほぼ同じ意味で使われますが、医学用語としては「疼痛」がより専門的な表現として用いられます。
国際疼痛学会では、
「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する、あるいはそれに似た、感覚かつ情動の不快な体験」と定義されています。
(引用:https://jasp.pain-research-jasp.org/pdf/notice_20200818.pdf)
簡単にいうと、
「痛み」は、体が傷ついたときや、傷つきそうな時に感じる、嫌な感覚やつらい気持ちのことです。
たとえ怪我をしていなくても、「痛い」と感じることがあり、それも痛みとして脳が反応しています。
痛みは感覚だけでなく、気持ちや状況にも深く関わっています。

痛みの特徴
| 項目 | 内容 |
| 感覚的側面 | どこが どのくらいの強さ どのくらいの時間 どんなふうに(鋭い、鈍い、刺すような、など) |
| 情動的側面 | 痛みでどんな気持ちになるか (苦痛、不安、恐怖、イライラ など) ※痛みによって気持ちの落ち込みやストレスが強くなることもある |
| 認知的側面 | 痛みの意味づけ (「これはやばいケガかも」「いつ治るのか」「これは一時的だから大丈夫」などの考え) ※同じ痛みでも人によって違う ポジティブな捉え方が、痛みの感じ方を軽くすることもある |
| 社会的側面 | 生活や人間関係への影響 「仕事ができない」 「家族に心配をかける」 「生活への影響」 ※痛みは本人の身体だけでなく、生活全体に影響する |
痛みの種類
痛みの種類は大きく3種類に分けられます。
侵害受容性疼痛
侵害受容性疼痛とは、身体の組織(皮膚・筋肉・関節・内臓など)が傷ついたり、炎症を起こした時に感じる一般的な痛みのことです。
□特徴
・一時的で治りやすい
原因がなくなれば自然に回復しやすい
・原因がはっきりしている
怪我、炎症、打撲など
・炎症を伴うことが多い
赤くなる、熱をもつ、腫れる
・一種の警告
体を守るための重要な信号
□よくある例
・捻挫や打撲
組織が損傷し、センサーが反応
・関節痛
炎症による持続的な痛み
・やけど
熱による組織損傷と痛み
・筋肉痛
筋組織の微細な損傷
□痛みのメカニズム
体が傷つく(怪我、炎症など)
↓
痛みセンサー(侵害受容器)が反応
↓
神経を通って脳に「痛い!」と伝達
(末梢神経→脊髄→脳)
↓
脳が痛みとして認識する
□治療法
・鎮痛薬(ロキソニン、カロナールなど)
・冷却・安静・圧迫・挙上
・物理療法(温熱、マッサージ、電気刺激など)
侵害受容性疼痛は、私たちにとって最も身近でわかりやすい痛みです。
多くの場合、打撲や捻挫、炎症など原因がはっきりしているため、適切な処置やケアが行いやすいという特徴があります。
ただし、痛みが長引いたり、慢性化したりすると、神経障害性疼痛や心因性疼痛など別のタイプの痛みに移行することがあり、注意が必要です。
神経障害性疼痛
神経障害性疼痛とは、神経そのものが損傷したり、傷害を受けることによって起こる痛みのことです。
通常の怪我による痛み(侵害受容性疼痛)とは異なり、神経のトラブルが原因で、痛みの信号が異常に働いてしまう状態です。
神経は「痛みを伝える配線」のようなものですが、この配線自体が壊れたり、誤作動を起こすと、本来痛くない刺激でも痛みとして感じたり、何もしていないのに勝手に痛み信号が出たりします。
□特徴
・焼けるような痛み
「ヒリヒリ」「ジンジン」「灼熱感」
・電気が走るような痛み
ピリッと刺すようなショック感
・軽い刺激でも強い痛み
風があたるだけでも痛い(アロディニア)
※アロディニアとは…
本来痛みを感じないはずの刺激なのに痛いと感じてしまう異常な状態
・しびれ・感覚の鈍さ
感じにくさと同時に痛みがある
・持続的に続く
夜間や安静時にも痛みが出ることが多い
□よくある例
・帯状疱疹後神経痛
帯状疱疹の後に神経が損傷して痛みが出る
・糖尿病性神経障害
高血糖により末梢神経が障害される
・ヘルニアによる神経圧迫
椎間板ヘルニアで神経が圧迫される
・手術・外傷
手術後や事故後に神経が切断・損傷される
・脊髄損傷
脊髄レベルでの神経損傷により慢性的な痛みが生じる
□痛みのメカニズム
末梢神経や中枢神経が損傷・圧迫・変性(ヘルニア、帯状疱疹など)
↓
神経が本来ないはずの刺激に過敏になったり、勝手に信号を発したりする
↓
何もしていないのに「痛み信号」が脳に伝わる(興奮状態)
↓
脳が「痛み」として誤って受け取る
・神経が壊れている、過敏になっている
・通常の刺激でも痛い、刺激がなくても痛い
□治療法
・神経調整薬(プレガバリン(リリカ)、ガバペンチンなど)
・抗うつ剤(デュロキセチン、アミトリプチリンなど)
・局所麻酔薬(リドカイン外用薬、神経ブロックなど)
・リハビリ・物理療法
・心理的ケア
※通常の鎮痛剤が効きにくい
神経障害性疼痛は、神経そのものが壊れたり誤作動を起こすことで生じる痛みであり、焼けるような感覚や電気が走るような痛み、痺れなど、独特でつらい症状を伴います。
一般的な鎮痛剤では効果が出にくく、専門的な治療が必要とされます。
また、痛みが長期化しやすく、心理的ストレスや生活への影響も大きいため、身体だけでなく心や社会面へのサポートも重要です。
心因性疼痛
心因性疼痛とは、身体的な損傷や炎症が見つからないにもかかわらず、実際に「痛い」と感じているのが特徴で、心理的・感情的な要因が強く関与しています。
「心のストレス・不安・過去のトラウマなどが原因となって、体に痛みとして現れる状態」です。
これは、「気のせい」ではなく、脳や神経が本当に痛みとして処理してしまっている、れっきとした「痛み」です。
痛みの感覚は脳で感じているものです。
強いストレスや心の不調があると、脳の痛みに関係する部分(扁桃体、前頭前野、帯状回など)の働きが変わり、実際には刺激がなくても痛みが出る、あるいは痛みが過剰に強く感じられることがあります。
□特徴
・検査で異常が見つからない
MRI・CT・血液検査で異常なし
・訴える痛みが多様
頭痛・腹痛・腰痛・関節痛など様々
・痛みが移動する・変化する
昨日は腰痛、今日は腹痛、明日は頭痛など
・不安や鬱傾向を伴うことが多い
心の状態と痛みが連動して悪化したり改善したりする
・生活機能にも影響
疲れやすい、眠れない、動けないなど生活面とも重なることがある
□よくある例
・心因性腹痛
ストレスや不安が引き金で腰が痛くなるが、画像では異常なし
・緊張型頭痛
心の緊張・精神的プレッシャーが原因で頭痛が起こる
・心身症(身体表現性障害)
感情の問題が体の症状として表れる(痛み、吐き気、動悸など)
・過敏性腸症候群(IBS)
ストレスで腸が敏感になり、腹痛、下痢などが繰り返される
□痛みのメカニズム
心理的ストレスや感情の問題が発生
↓
脳の「痛み制御システム」が乱れる
↓
脳が「痛みをつくり出す」
↓
本当に「痛い」と感じる
□治療法
・心理療法
考え方の癖や感情の扱い方を調整
・抗うつ薬・抗不安薬
神経系のバランスを整え、痛みを軽減
・カウンセリング・心のケア
痛みの原因に向き合うサポート
・リハビリ・軽い運動
身体の機能を取り戻す
自信をつける
・社会的サポート
家族や職場の理解、協力も大切
心因性疼痛には、身体に明らかな異常がなくても本人が実際に「痛い」と感じる痛みです。
その背景には、ストレスや不安、抑うつなどの心の状態が大きく関与しており、頭痛・腰痛・腹痛など、さまざまな形で表れるのが特徴です。
痛みの軽減には、身体的なケアだけでなく、心理的なサポートも含めた心と体の両面からの対応が重要となります。

痛みの役割
「痛み」は私たちの体にとって非常に重要な防御システムとして働いています。
痛みがあるからこそ、私たちは怪我や病気に気づき、対処し、回復に向かうことができます。
□危険のサイン(警告機能)
「体に異常が起きている」ということを知らせる信号です。
内臓の病気や感染症など、見えない異常にも気づかせてくれます。
痛みがなければ、怪我や病気に気がつかず、悪化や命に関わることもあります。
□体を守り、回復を促す
痛みがあることでその部分をかばい、安静にすることができます。
無理をしないように体を守る働きをしてくれます。
□周囲に助けを求めるきっかけ(社会的な役割)
痛みやそれに伴う体の異常を周囲に伝えることで、共感を得たり支援を受けることができます。
痛みの訴えは、人とのつながりやケアのきっかけにもなります。
□もし痛みがないと…
先天性無痛症(生まれつき痛みを感じない病気)の人は、
・骨折ややけどに気づかず悪化する
・感染症や内臓の異常に気づかない
・自然に体が壊れていくことも…
痛みは「なくなったら困る」大切な命のセンサーです。
痛みが及ぼす悪影響
痛みは本来、体を守るための大切サインですが、長引いたり、強すぎたり、適切に処置されなかった場合には、心身にさまざまな悪影響を及ぼします。
特に慢性化した痛みは、本人の生活、心、身体、社会的つながりに大きなダメージを与えることがあります。
□身体への悪影響(からだ)
・運動量の低下・運動不足
痛みがあることで動かなくなり、筋力・柔軟性が低下
・回復力の低下
血流・免疫力が落ちて、自然治癒が遅れる
・姿勢・バランスの崩れ
かばう動作が続き、他の部位にも痛みや負担が広がる
・薬の副作用リスク
鎮痛薬の長期使用による胃腸障害、腎機能への影響など
□精神・心理面への悪影響(こころ)
・抑うつ・不安・孤独感
「このまま治らないのでは?」「誰にもわかってもらえない」などの苦悩
・不眠・睡眠障害
痛みで寝付けない
途中で目が覚める
・イライラ・怒りっぽい
痛みがあることで環状のコントロールが難しくなる
・自尊心の低下
「できない自分」に落ち込み、自己評価が下がる
□社会的な悪影響(くらし・人間関係)
・仕事・家事への支障
通勤や作業ができなくなる
休職や退職につながるなど
・人間関係の悪化
痛みを理解されず、家族内や職場で孤立する
・経済的負担
医療費の増加や収入の減少、生活の質の低下
□痛みの悪循環
痛みはそれ自体がストレスになり、ストレスがまた痛みを悪化させるという「負のループ」を生じさせます。
東洋医学から見た痛み
東洋医学では、痛みは単なる「組織の損傷」ではなく、「気(エネルギー)・血・水」の流れの乱れや滞りによって生じる現象と考えられています。
つまり、体内のバランスの乱れが痛みの根本的な原因とされます。
「不通則痛(ふつうそくつう)」=流れなければ痛む
を基本として考えます。
気や血がスムーズに流れていないと、そこに滞り(瘀血や気滞など)が起きて痛みになります。
| タイプ | 原因 | 特徴 |
| 瘀血(おけつ) ※実証 | 血の流れが悪い | 刺すような痛み 固定性 夜間に悪化 |
| 気滞(きたい) ※実証 | ストレス・抑うつなどで気の流れが滞る | 張るような痛み 場所が変わる |
| 虚証(きょしょう) | 体力・気・血・水などが不足した状態 | 慢性的 鈍くて重い痛み 疲れると悪化(夕方~夜) 冷えやすい |
| 邪気(じゃき) 風邪・熱邪・湿邪・燥邪・寒邪 | 「自然界に存在する体に悪影響をおよぼす要素」が体の中に入ってくる | 風邪(ふうじゃ): ・移動性の痛み、動きが早い ・症状が悪化しやすい 熱邪(ねつじゃ): ・炎症、腫れ、熱感、ズキズキ、赤み ・体力を奪う疲労性の痛み 湿邪(しつじゃ): ・重だるい、長引く ・関節や筋肉に絡みやすい 燥邪(そうじゃ): ・乾燥による粘膜や皮膚の痛みや 痒み 寒邪(かんじゃ): ・体を冷やす ・血流を停滞させる ・刺すような痛み |
※実証とは…
エネルギー過多・詰まりがち・疎泄できない状態を指します。
痛みへの鍼灸アプローチ
東洋医学の「痛み」への考え方は、「バランスが崩れた結果」として痛みが起こっていると考えます。
痛みに直接アプローチする西洋医学とは違い、「気・血・水」の巡りを整える間接的なプローチをすることで、痛みを取り除きます。
□実証へのアプローチ
実証による痛みは「強い、急性、明確」なことが多いです。
過剰になっているものを取り除き、流れを良くすることで改善が見込めます。
瀉法(しゃほう)で、「抜く、散らす」ことを中心に施術を行います。
ただし、強すぎる刺激には注意が必要です。
やりすぎるとかえって悪化させてしまう場合があります。
□虚証へのアプローチ
虚証による痛みは「足りない、弱っている」ことで起こります。
補法(ほほう)で、足りないものを補うことで改善が見込めます。
また自己治癒力を高めて、体を内側から元気にすることが根本的な改善に繋がります。
優しい刺激で施術をすることが多いです。
□邪気へのアプローチ
邪気による痛みは「侵入してきた邪気を追い出すこと、邪気が滞らせた気血の巡りを良くする」ことで改善が見込めます。
それぞれの邪気に応じた経穴(ツボ)を使い、巡りを改善させ、症状を和らげます。

まとめ
痛みとは、感覚、感情、社会的な要素が関わってくる複雑なものです。
実際の怪我だけでなく、目に見えない痛みというものは確実に存在します。
西洋医学と東洋医学では違う考え方をしますが、それぞれ痛みにはいくつか種類がありました。
ご自分の痛みは何に当てはまるのかわかりましたか?
専門的なことが多く難しいところもあったかもしれませんが、なにか痛みに関して不安なことがあれば、まずかかりつけ医に相談してみるといいかもしれません。
「よくわからないけどつらい」といった不定愁訴は東洋医学をメインと考える鍼灸院や漢方外来などに相談するのもいいでしょう。
私たち鍼灸師は西洋医学と東洋医学の観点からお体を診て施術方法を考えています。
誰に相談したらいいかわからない痛みについて、一度私たちに相談してみませんか
ここまで、読んでいただきありがとうございました。