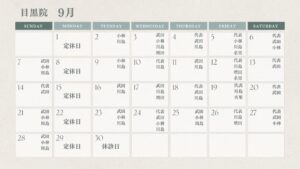こんにちは。Bianca鍼灸サロンです。
今回は『片頭痛』について記事を書きました。
頭が痛いと仕事の効率も下がるし、何をやるにもなかなか気分が乗りません。
「今日の予定をキャンセルしようかな。しんどい。」
朝から頭が痛い時なんて最悪な気分です。
人によって痛みの感じ方が違うので、なかなか理解されないこともあると思います。
- 片頭痛とは
- 頭痛の役割
- 頭痛が及ぼす悪影響
- 東洋医学から見た片頭痛
- 片頭痛への鍼灸アプローチ
Biancaブログでは患者様が気になっていることをブログにしております。
他にもこんなことも知りたいなどあれば、お問い合わせください。
皆様、最後までお付き合いいただければ幸いです。
片頭痛とは
「頭がズキズキ痛む」
脳の血管や神経の異常な反応によって起こる、発作的な頭痛です。
痛みの度合いによっては生活に大きな影響を与えることがあります。

痛みについて
| 項目 | 内容 |
| 痛む場所 | 片側が多い 両側になることもある |
| 痛みの性質 | ズキズキ・ガンガンとした、脈を打つような拍動性の痛み |
| 強さ | 中~強程度 日常生活が送れなくなることもある |
| 持続時間 | 数時間~72時間程度 |
| 頻度 | 月に1~4回程度が多い 慢性化することもある |
| その他 | 吐き気・嘔吐・光・音・匂いへの過敏 視覚異常が伴うこともある |
| 前兆 | 【前兆ありタイプ】 視界にチカチカした光、ギザギザした模様、視野欠損など 片側のしびれや言葉が出にくいこともある 通常前兆は5~60分間続いた後に頭痛が始まる 【前兆なしタイプ】 ほとんどの方はこちら 突然ズキズキと痛み出す |
主な原因
□血管の拡張
頭の感覚をつかさどる三叉神経が活性化し、炎症性物質を放出
その結果、血管が拡張し周囲の神経が刺激されて痛みが出ている可能性が高いと言われている
□脳内神経の過敏
光・音・匂いへの感受性が高い方が多い
□ストレスやホルモン
過度なストレスがかかると交感神経優位になり血管が収縮します。
その状態から急に副交感神経優位の状態になると、血管が拡張することで一気に血流が良くなり頭痛が起こります。
ホルモンバランスが崩れると、エストロゲンの低下などにより生理前に頭痛が起こりやすくなります。
片頭痛の正確な「根本原因」は、まだ完全には解明されていません。
しかし、「引き金(トリガー)」が特定されており、発症のしくみは理解が進んでいます。
引き金(トリガー)
□ストレス・ホッとした時
□寝不足・寝過ぎ
□ホルモンの変化
□食べ物・飲み物
(チョコ、ワイン、コーヒー、チーズなど)
□空腹や脱水
□天気・気圧の変化
□強い光・音・匂い
画像検査や血液検査で異常が出にくいため、原因不明とされることもあります。
しかし実際には神経・血管・ホルモンの働きが密接に関与しており、体質と外部からの刺激が重なった時に症状が現れやすくなります。
そのため、原因よりも「きっかけ」に注目することが重要視されます。
対処法
□痛み止めを飲む
月に10日以上使用している場合は薬物乱用性頭痛に注意
□静かな暗い場所で安静にする
光・音・匂いの刺激を遮断する
□冷やす・温める
一般的には額やこめかみを冷やすことが有効
(拡張した血管を収縮させる)
ただし、首や肩が緊張している場合は温めたほうがいいこともある
(緊張型頭痛との混合型の場合)
□吐き気がある場合は食べずに休む
胃腸の働きが落ちているため、食事やサプリを摂るのはNG
脱水状態を避けるため、水分は少量ずつ補給
避けたほうがいいこと
□頭を揉む・叩く
血管を刺激して悪化する可能性がある
□お風呂に入る
血管がさらに拡張して、痛みが強くなる可能性がある
□運動・外出
光や音、身体の負担で症状が悪化することが多い
□PC、スマホを使い続ける
画面の光が刺激になり、長引かせる原因になる
予防法
□ストレスコントロール
瞑想・ヨガなど
□睡眠リズムを整える
寝過ぎ、寝不足を避け、同じ時間に起床・就寝する
□食事管理
空腹を避けチョコ・ワイン・コーヒーなどの摂取をコントロールする
□水分補給
脱水が誘因になることもあるため、こまめの水分補給をこころがける
□頭痛ダイアリー
頭痛の起こるパターンや食事・行動を記録し、原因を特定するのに役立つ
※受診の目安
次のような場合は、医療機関(頭痛外来・神経内科)の受診をおすすめします。
□今までと違う強い頭痛が突然来た
□頭痛と共に手足のしびれ、言語障害、けいれんなどがある
□市販品が効かない、頻繁に再発する
□日常生活に支障をきたしている
頭痛の役割
一見ネガティブにしか見えない頭痛にも「体からのサイン」という意味でメリットが存在します。
体の異常を早期に知ることができる
脳・血管・目・首などの不調に気づくことができる。
脳出血、頚椎症などの初期症状として現れることで、深刻な状況になる前に病院で検査を受けることが可能です。
自分の限界を気づかせてくれる
「もう限界だ」ということが頭痛というかたちで現れています。
このまま頑張り続けていると慢性的な頭痛やうつ病などの精神疾患につながる可能性もあります。
少し休んで身体を回復させましょう!
また自分の生活習慣を見直しするきっかけになります。
睡眠の質・時間、食生活、過度なストレスなど普段と違っていたものは調子のいい時の生活スタイルに戻しましょう!
感受性や敏感さの表れ
片頭痛持ちの人は、光・音・匂い・気圧・人間関係などに敏感なことが多いです。
これはネガティブに捉えられがちですが、直感が鋭い、空気を読めるという特性でもあります。
「敏感さ=弱さ」ということではなく、「敏感さ=感受性」と考えられます。
頭痛そのものはつらいですが、それを「身体からのメッセージ」として捉えることで、痛みの原因を見つけ、痛みのない本当の意味で元気な状態に近づけるきっかけになります。
頭痛が及ぼす悪影響
頭痛があることでのデメリットは「痛い」だけではありません。
日常生活や仕事にも影響を及ぼす場合があります。
身体的デメリット
□集中力の低下
作業効率が落ち、仕事や勉強のパフォーマンスが落ちます。
□睡眠の質の低下
痛みで眠れない可能性が出てきます。
浅い眠りになり、睡眠時間が取れていても疲れがちゃんととれないこともあります。
□痛み止めの多用による副作用
胃腸障害、薬物依存、薬物乱用頭痛を引き起こす可能性があります。
精神的デメリット
□イライラ・不安感の増加
慢性的な痛みが続くことで精神的なストレスが溜まりやすくなります。
ホルモン・気候・生活の変化に敏感で、体調のコントロールがしにくくなります。
社会的デメリット
□仕事・家事・学業への支障
欠勤、遅刻が増えたり、作業効率が低下します。
結果的に評価や信頼にも影響が出ます。
□周囲とのコミュニケーションへの影響
痛みによって人と関わる気力がなくなったり、趣味が減り、生活の質が低下する可能性があります。
それにより、孤独感を感じることもあります。
東洋医学から見た片頭痛
東洋医学で診た時の片頭痛は、脳の病気や神経の異常などではなく、「気・血・陰陽・五臓六腑(特に肝)」のバランスの乱れが原因で起こると捉えます。
肝陽上亢(かんようじょうこう)タイプ
肝陽上亢とは、「肝の気(エネルギー)」と「肝の陽(熱エネルギー)」が上昇し過ぎている状態のことです。
怒りやストレスによって、気のコントロールが乱れ、熱エネルギーが頭にのぼります。
痛みについて
| 項目 | 内容 |
| 痛みの場所 | 頭頂部~側頭部、後頭部にかけて出ることが多い |
| 痛みの性質 | ズキズキ、ガンガンする強い痛み (拍動性のこともある) |
| その他 | のぼせ、目の充血、耳鳴り、めまい、怒りっぽい、口が苦い、顔のほてり |
| 性格の傾向 | 完璧主義、我慢強い、負けず嫌い、怒りを抑えるタイプ |
| 悪化要因 | 強いストレス、怒り、精神的な緊張、睡眠不足、アルコール |
主な原因
□ストレスの抑制
□陰虚(身体を冷ます力の不足)
□生活習慣の乱れ(睡眠不足や過労)
□辛いもの・アルコールの摂り過ぎ
気滞血瘀(きたいけつお)タイプ
「気(エネルギー)」と「血(栄養)」の流れが両方とも滞ってしまった状態です。
この2つが合わさると、詰まりによる頭痛として片頭痛が起こります。
慢性的なストレスや疲労の蓄積型の片頭痛に多いのが特徴です。
痛みについて
| 項目 | 内容 |
| 痛みの場所 | 片側(こめかみ・側頭部)または局所に固定的に出やすい |
| 痛みの性質 | 鈍痛、ズーンと重たい痛み 刺すような痛み |
| 持続 | 慢性的に続く 時々ズキっと鋭く痛む |
| その他 | 肩こり、目の疲れ、胸のつかえ、月経トラブル(塊、痛み) |
| 悪化要因 | ストレス、感情の抑圧、長時間の同じ姿勢、冷え、不安定な生活リズム |
主な原因
□ストレス・怒り・我慢
□気の流れが悪い
□血の流れが悪い
□生活習慣
□ホルモンバランスの変化(月経周期など)
痰濁阻滞(たんだくそたい)タイプ
体の中に「余分な水分(痰湿)・老廃物」がたまっている状態です。
これは鼻水の痰だけでなく、体の中の湿気、ベタついた重さ、つまり感など広い意味があります。
それが頭部に影響して頭痛や吐き気、めまいを引き起こします。
痛みについて
| 項目 | 内容 |
| 痛みの場所 | 前頭部、側頭部、全体的に感じることもある |
| 痛みの性質 | 重だるい、モヤモヤする、圧迫されるような痛み |
| 時間帯 | 雨の日、湿気の多い日、満腹時、朝起きた直後に悪化しやすい |
| その他 | 吐き気、食欲不振、胃のムカムカ、めまい、胸のつかえ、舌に白い苔がべったり |
| 体質 | 胃腸が弱い、むくみやすい、肥満気味、だるさが取れない |
主な原因
□雨の日、梅雨、湿気の多い時期
□胃腸の働きが弱っている
□運動不足
血虚(けっきょ)タイプ
西洋医学的にみた、貧血と少し似ています。
血の不足、もしくは、血があっても栄養が不足している状態です。
これは脳や筋肉に必要な栄養が行き渡らず、頭痛やめまい、疲労感などの症状が現れます。
痛みについて
| 項目 | 内容 |
| 痛みの場所 | 頭頂部が多い、または広範囲に広がる |
| 痛みの性質 | 鈍い、重だるい、ぼーっとする、ふわっとした感じ |
| 頻度・タイミング | 疲労時、生理中やその後、寝不足時に出やすい |
| その他 | めまい、目のかすみ、動悸、顔色が白い、爪が割れやすい、眠りが浅い、月経量が少ない、集中力が低下している |
| 体質 | 痩せ型、冷え性、虚弱体質、胃腸が弱い |
主な原因
□長期的な過労やストレスで「血」の消耗
□食事の偏りや胃腸が弱く「血をつくる力」が不足
□月経・出産等で血の大量消耗
□睡眠不足や精神的な疲労による血の消耗
腎精不足(じんせいぶそく)タイプ
腎精は生命力のもとになる根本的なエネルギーです。
発育、老化、脳、骨、髄、ホルモン系、生殖機能、免疫力などを支えます。
痛みについて
| 項目 | 内容 |
| 痛みの場所 | 頭頂部や後頭部が中心 |
| 痛みの性質 | 慢性的で鈍い、ぼーっとする、ふわふわした感覚 |
| 時間帯 | 疲れた時、夕方以降、性交後、月経後など |
| その他 | 耳鳴り、めまい、物忘れ、腰や膝のだるさ、疲労感、不妊、生理不順、白髪、抜け毛、夜間頻尿 |
| 体質 | 中年以降、慢性疾患を患っている人、過労、出産後、病後の回復期 |
主な原因
□加齢
□過労・睡眠不足
□生殖活動の負担
□慢性病
片頭痛への鍼灸アプローチ
鍼灸施術では痛みを和らげることだけでなく、発作の予防、体質改善、自律神経やホルモンの調整など総合的な観点から施術を行います。
自律神経へのアプローチ
鍼灸施術は自律神経へのアプローチが可能です。
興奮状態である交感神経過緊張を抑え、リラックス状態の副交感神経優位に切り替える作用があります。
片頭痛は、血管の拡張や脳内神経過敏、ホルモンの変化など自律神経が関係しているため、自律神経のバランスを整えることが大切です。
ツボへのアプローチ
ツボを通して全身の巡りに働きかけることで、心と身体のバランスを根本から整える力があります。
特に自律神経系に働きかけることで、交感神経と副交感神経のスイッチをうまく切り替えやすくなり、ホルモンバランスが整ってくる方も多くいらっしゃいます。

まとめ
ここまで、読んでいただきありがとうございます。
片頭痛は「ズキズキと脈打つような痛み」が頭の片側(両側のこともある)に起こる頭痛です。
繰り返す発作的な頭痛であることが特徴です。
片頭痛のはっきりとした原因は不明ですが、「脳の血管が拡張し、三叉神経が刺激されること」や「セロトニンなど神経伝達物質のバランスの乱れ」が関係すると言われています。
鍼灸施術では自律神経やホルモンバランスの調整など、全身へのアプローチが可能なため根本からの改善につながります。
病院へ行っても原因がわからなかった頭痛をお持ちの方は、一度視点を変えてみましょう。
東洋医学の観点から頭痛について考えてみると頭以外のところに原因が隠れているかもしれません。気になった方はぜひ鍼灸治療を受けてみませんか?